|
6 点検の基準年数
適正な管理の周期
設備・施設の点検に基準(保安規定)が存在します。
受変電設備のキュービクルなど、自家用電気工作物には法定点検が義務付けられています。
保安規定で定められた点検では、各設備で巡回点検、定期点検、細密点検が行われます。
例えば、遮断器類については
巡回点検(1か月)、定期点検(1年)、細密点検(12年)の周期が決められています。
ここで、疑問が出てきます。この基準を守るだけで良いのでしょうか?
保安規定を守っています。規定上は問題はありません。
ただ設備の維持管理はこの基準によるだけのものではありません。
新設した遮断器の12年目の点検、24年経過し、まだまだ、更新されていません。
しかし、「その後の細密点検は12年でいいの?」となります。
中々設備更新が進まず、設備は徐々に老朽化し、部品交換もできなくなります。
当然そこには、経年劣化を加味しなければいけません。
普通に考えれば、古くなった場合や環境が悪く劣化が早い場合は、細密点検の期間を6年、4年と短くする必要があるでしょうし、修理も行わなければなりません。
ただ規定にはこのことが記載されていません。当たり前のことだからです。
ただ、ここで問題が生じます。
細密点検を短くしたり、修理するとなるとそれなりの予算を計上しなければいけません。
予算を計上するには、「なぜ短くするのか」の合議の説明資料が必要です。
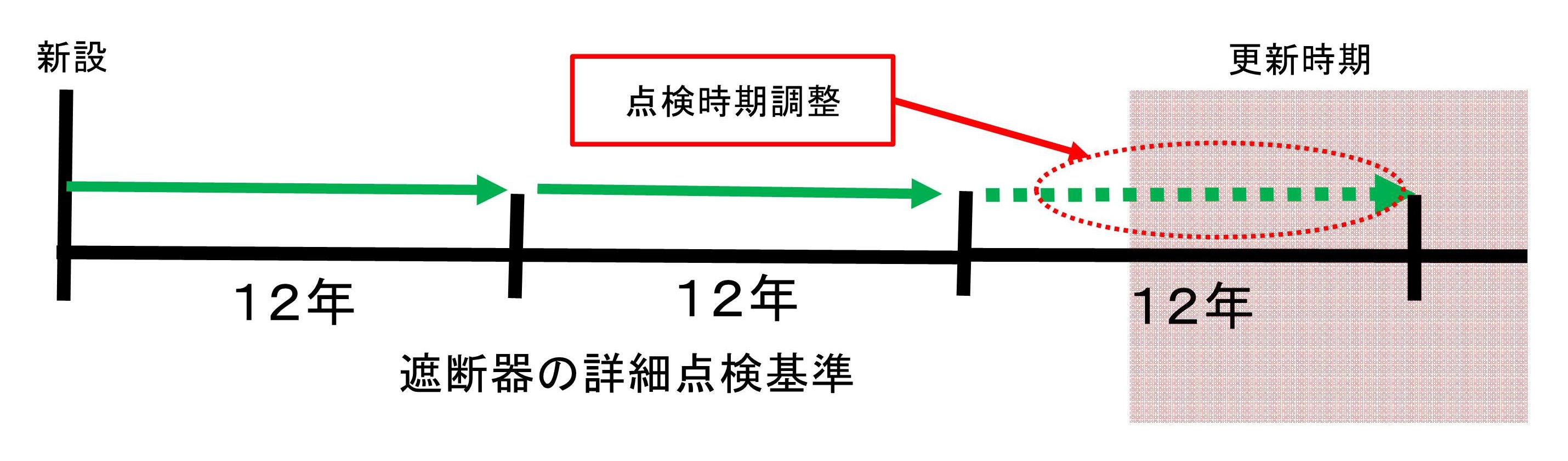
ここで、日々「忙しい(あるいは手間の手抜の)技術者」は、そのまま12年のままでいいやとなります。
幸いにして、36年後?又は更新により何事もなく間に合うかもしれません。しかし運悪く、間に合わないかもしれません。
そのときは重大故障(事故)です。
基準は守っていたので責任は問われないかもしれません。でも、技術屋の良心にはもやもや感が大いに残ります。
|